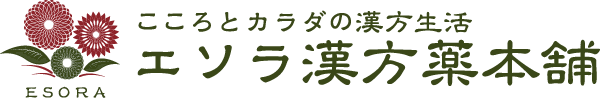明治時代、熊本県阿蘇郡小国町で「漢学(中国伝来の漢籍・中国思想・漢詩文の研究)」を学ぶ少年がいました。
少年の父は庄屋(現在の村長のような役職)で厳しく育てられ、8歳で伯父の漢学者にあずけられて学問を学びます。
彼の両親はもともと医者の道を勧めていましたが、少年は暴れん坊で、軍人になることを志し「医者と坊主には絶対にならない」と言い放っていたといいます。
そんな中、1858年から「コレラ」の世界的大流行があり、少年は弟2人と妹を立て続けに「コレラ」で亡くすことになります。
このことがあり、彼は親の勧めでもある医者になって世の人たちを助けたい気持ちが強くなり、もっと勉強しなければならないと考えます。そして上京し、東京医学校(現在の東京大学大学院医学系研究科・医学部の前身)に入学します。
彼の家は兄弟が多く生活が大変なので、家からの仕送りはなく牛乳屋でアルバイトをしながら学費を稼ぎました。東京医学校で猛勉強をし、医学部在学中に学生集会でこんな言葉を述べています。
「人民に摂生保健の方法を教え体の大切さを知らせ、病を未然に防ぐこと」
彼はこの時代に「治療」より「予防」の重要性を説いていたのです。
東京医学校時代、彼の運命の変えることになるオランダ人軍医の「マンスフェルト」先生と出会います。顕微鏡を用いて動植物の細胞を見せられたことから、微生物の世界に興味を持つようになりました。
卒業後、一般的に高給取りになれる病院ではなく、給料が半分以下になる内務省(現在の厚労省)の仕事を選びます。コレラなどの研究、予防医学の普及と研究に力を入れたいというのが目的でした。
そして研究が実り、コレラの原因究明で多くの命が助かることになります。その功績が認められ、彼はドイツに留学し「ローベルト・コッホ」先生の指導で学びます。
ドイツで研究する中、彼は難しい伝染病を知ります。土の中の微生物が原因で感染症がおこる病気「破傷風」です。
破傷風菌の中毒症状は、筋硬直・筋痙攣・自律神経障害などが起こり、絶命するまで苦しめられる恐ろしい病気です。特に子どもたちの感染は多く、新生児に関しては80%~90%の死亡率でした。
彼は研究に研究を重ねましたが、大きな壁にぶつかり苦戦します。破傷風菌はほかの細菌と混ざり、破傷風菌を取り出して培養することは当時の技術では困難を極めたといいます。それでも彼は諦めずに続けました。苦しんで亡くなる子どもたちに、自分の弟妹を亡くした記憶が思い出されたのかもしれません。
そしてついに、誰もできなかった破傷風菌を取り出し純培養することに成功します。破傷風の原因は「細菌そのものではなく細菌が作り出す毒」だということに気づき、免疫抗体を使って治療する方法を発明し、世界的に有名になります。
彼はそれから日本に帰国して伝染病研究所の設立に動く中で、援助をしたいという人物が現れます。支援者自身の所有する芝公園内の土地に伝染研究所を建設し、研究用の機器の寄付を働きかけ彼を支援します。この惜しみない援助をしたのが福沢諭吉でした。
当時(明治時代)も伝染病はいくつか流行しており、彼は日本のために伝染病の研究し貢献します。
2年後、中国南区から香港まで多数の死者が出ている伝染病が蔓延し、明治政府は彼を中心とする調査団を派遣。彼はこの病原菌と戦うこととなります。
その病気は、100年ぶりに現れた「ペスト」。
彼はなんと、調査の初日に「病原菌と思われる細菌」を患者の血液、脾臓から見つけることに成功。病原菌を特定し、発見はイギリスの医学誌にも掲載されることになります。
その後も、狂犬病やインフルエンザ、赤痢などの血清開発を続け、後進の指導にも熱心に取り組みます。ハブ毒の血清療法を確立した「北島多一」、赤痢菌発見者の「志賀潔」、梅毒の特効薬を創設した「秦佐八郎」、寄生虫が媒介する病気の研究で業績をあげた「宮島幹之助」、黄熱の研究で有名な「野口英世」など優秀な研究者を輩出しています。
彼は支援してくれた福沢諭吉の恩に報うべく、没後15年目に慶応義塾大学医学部を創設し、初代科長、病院長に就任しました。
治療より予防を考え、日本の近代医学を築いた彼は、1931年6月13日、78歳の生涯を閉じました。
彼の名は、近代医学の父といわれた「北里柴三郎」先生です。
北里柴三郎は、研究に行き詰まった際に勇気づけた言葉があります。
「君、人に熱と誠があれば、何事でも達成するよ。よく世の中が行き詰ったという人があるが、これは大きな誤解である。世の中は決して行き詰まらぬ。もし行き詰まったものがあるならば、これは熱と誠がないからである。つまり行き詰まりは本人自身で世の中は決して行き詰まるものではない。熱と誠とをもって十分に学術を研究したまえ」
この言葉を大事にし、研究者たちは医科学者として大成したといいます。北里柴三郎が、さまざま体験し、何事にも諦めず挑戦し続けた体験を伝えた言葉だったのでしょう。
北里柴三郎は、2024年の今年、新紙幣の千円札に登場し、みなさんに「熱」と「誠」を新たに伝えることだと思います。